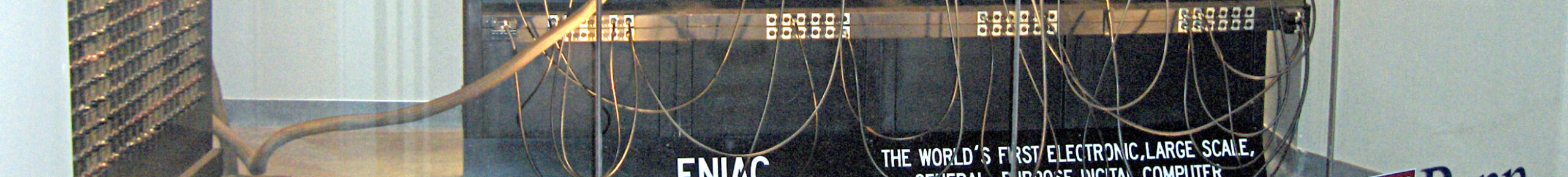カテゴリー: ブログ
-
支部委員だより
ソフトウェアセクション委員長の仲村です。 コロナ禍で休止していたイベントを久しぶりに開催できましたので、ご報告…
-
本の紹介:東アジアの歴史
唐突ですが、私は歴史系が好きです。 若い頃は時代小説等よく読んでいました。 今は韓国時代劇を観たりするのが好き…
-
花を生ける
生け花を始めてン十年になる。 伯母が華道師範(生け花の先生)をしていた関係で、半強制的に習い始めたものだった…
-
スマホで隙間時間の活動
4月から私の職場が変わって基本的に通勤になりました。落ち着いて読書をするには少し短い乗車時間ですので、スマホで…
-
久々のメーデー、久々の対面イベント
5月 1日、労働者の国際的な祭典であるメーデーが行われました。メーデーで代々木公園に大勢で集まるのは 2019…
-
動画紹介「ロシアの頭脳が流出する」
NHK BS1 で「ロシアの頭脳が流出する 〜世界の IT 産業は変わるのか〜」という番組を見ました。 「ウク…
-
本の紹介:経済社会の学び方 健全な懐疑の目を養う
著:猪木武徳中央公論新社 書名で検索すると、目次、内容、著者略歴が見つかるので、そちらもご覧頂きたい。 はじめ…
-
WordPress テーマ変更: Twenty Twenty-Three
このサイトの WordPress テーマを Twenty Twenty-Three に変更しました。普通のサイ…
-
インボイス制度反対! 財務省への中止要請
去る 4月14日、インボイス制度の中止要請を財務省にて行いました。 財務省に入るのは初めてですし、対面だけでは…
-
電算労・電算労組 合同定期大会 ~大幅賃上げを目指す ’23 春闘~
2月25日、電算労・電算労組 合同定期大会が行われました。 コロナウィルス感染防止のため今年も Web で行わ…