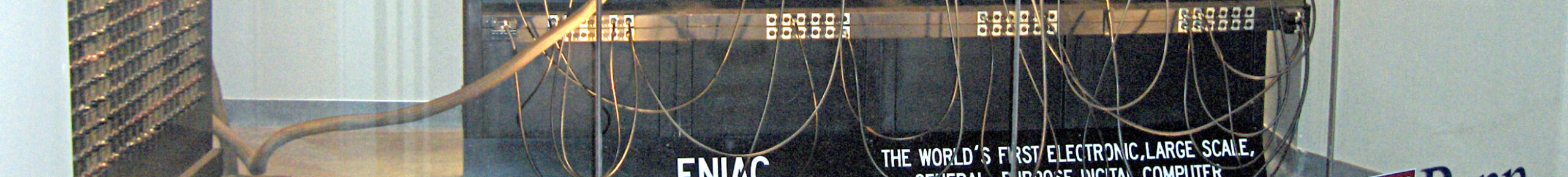2025年2月16日~17日、労供労組協学習会&幹事会が開催されました。
会場は川崎市の「かながわサイエンスパーク」。コンピュータ・ユニオンからは何名かの方が参加しました。
【学習会】
搾取の歴史に泣けてくる 「派遣に替わる労供の可能性と課題一歴史を振り返りながら考える」と題した龍谷大学法学部教授の武井寛先生の講演がありました。勉強になりました。
―1921年 職業紹介法制定
江戸時代から口入屋はあったが初の法制化。
ただし実態は一割から五割のピンハネ、強制貯蓄で足留めした労働者を同業者間で又貸して賃金が高くなるにつれてピンハネが積み上がり、「遂に賃金の体裁をなさないまでに差し引かれてしまふ」(勞働事情調査所編『臨時工問題の研究』(1935年))という有様。
…多重搾取構造、今とあまり変わらないような…
―1933年 ILOが有料職業紹介条約の批准と勧告 「日本の現状が遠く及ばないゆえ」国会で批准しない決定。
…動かない政治、今とあまり変わら…(以下略)
―1938年 職業紹介法の改定 失業対策と軍需動員のため職業紹介所を国営化。すべての事業で労務供給事業が可能になる。 戦時中は労務供給事業者、作業請負事業者や日雇い労務者などにより「産業報国会」ならぬ「労務報告会」が結成され戦時体制強化が進む。
―1947年 職業安定法の制定 GHQの指示により営利による供給禁止(ただし労働組合を除く)という現在の法律が作られました。
その後も、どのような労組に許可を与えるか、使用関係とは支配従属関係とはなんぞや、といった議論が繰り返さて度々指針の変更が行われました。
…行ったり来たりで変わらない現実。
「名ばかり労供」対策を厚労省に申し入れしてるけれど、今とあま…(以下略)
【幹事会】
めげずに進もう労供で 各加盟組合から事業報告を行いました。音楽家への公正な報酬を求める声明、労供で日雇い自動車運転業務を認めさせる取り組みなど、休止前と変わらず健闘する他組合の報告に勇気づけられました。コンピュータ・ユニオンからは組織と専門部活動を紹介しました。 労供労組協からは非正規公務員に労供を広めるプロジェクト構想と会費体系の変更について説明がありました。これは次の大会で正式決定されます。 今回は4つの大学から研究者に参加していただきました。経済学、社会学の両面から注目されているようで、先生方の活躍にも期待が広がりました。
■ コンピュータ・ユニオン ソフトウェアセクション機関紙 ACCSESS 2025年3月 No.449 より