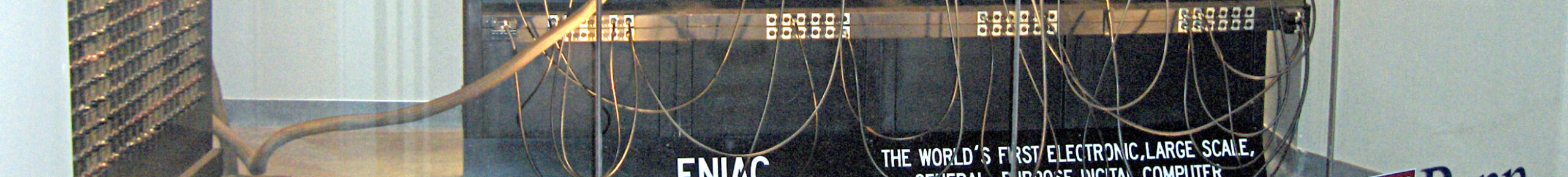カテゴリー: ブログ
-
電算労学習会「労働基準法改正のポイント」
2025年12月13日に、労働基準法改正のポイントをテーマとした電算労の学習会が行われました。 講師は、旬報…
-
2026年1月10日 電算労旗開き
2026年の電産労旗開きを開催しました。今年もよろしくお願いいたします。
-
謹賀新年
新年あけましておめでとうございます。 昨年は、組合活動にご協力をいただき、心より御礼申し上げます。 本年、…
-
学習会にも参加してます。学習の秋。
コンピュータ・ユニオンの関西IT支部では、IT技術者・クリエイターカフェという学習会が行われています。 10…
-
さよならWindows10。お疲れWindows10。
2025年10月14日にWindows10がサポート終了になりました。自分が関連するパソコンは一通りWind…
-
最後のリーフレット配布
コンピューターユニオンとしての最後のリーフレット配布は、10月12日の板橋区の城北中・高でした。 来年から…
-
大菩薩嶺行ってきました
6月の中旬に梅雨の合間を狙って日本百名山のひとつ大菩薩嶺に行ってきました。 稜線を歩いているときにも親子が…
-
委員長挨拶~今期もよろしくお願いいたします
2025年9月20日、コンピュータ・ユニオン ソフトウェアセクション第40回定期大会を開催しました。 事前に各…
-
朗読講座に参加して
最近、時々声がかすれるので、もっと声を出す機会を増やさなければと考えていたところ、妻が区報で「認知症予防のた…
-
情報処理技術者試験の応用・高度試験が2026年度からCBT方式に
IPAから情報処理技術者試験の応用・高度試験が2026年度からCBT方式になることが発表されました。したがって…