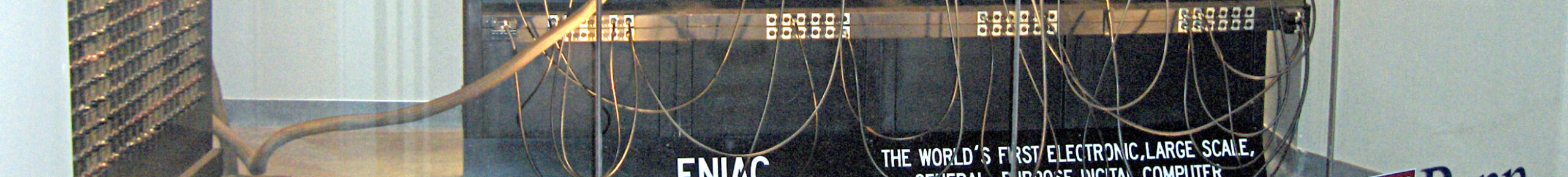2017年11月16日(木)19時より、新宿の外れの少しさびしい通りに面した小さなビルの2階の貸し会議室で、電算労秋の労働法学習会「情報サービス産業におけるブラック企業の傾向と対策」が開催されました。
講師は、ブラック企業被害対策弁護団の代表の佐々木亮弁護士(旬報法律事務所)です。佐々木弁護士は、私たち電算労の関係ではPUCの事件を担当されています。また、毎年最悪のブラック企業をWeb投票と審査で選ぶ「ブラック企業大賞」の企画委員会に名を連ねています。今年ももうそろそろノミネート企業の発表でしょうか。
以下、学習会の内容をかいつまんで紹介します。
「ブラック企業」という用語
「ブラック企業」という言葉は、他でもない情報サービス産業で生まれたものです。10年ほど前までは労働弁護団の中でも通じない言葉だったそうですが、文春新書「ブラック企業 日本を食い潰す妖怪」(著:今野晴貴)で 2chには縁のない上の世代にも知られるようになります。
今ではもう新語・流行語ではありません。日本語に定着した単語として広辞苑に載り、「ブラック○○」という言い回しが普通に使われるようになりました。情報産業に身を置く者としては全然うれしくありません。
ブラック企業がはびこる背景
現在の日本でブラック企業がはびこる背景の一つは、労働市場における売り手の弱さです。正社員の求人倍率はずっと1倍を下回っていました。今年はようやく1.01倍になりましたが、1倍を超えたのは厚労省が調査を始めた2004年以来初めてのことです。もしかして、四半世紀前のバブル崩壊以降ずっと1倍未満だったのでしょうか。そのような状況に置かれて、日本の独特の新卒一括採用から漏れると正社員になれないと悲壮な思いで就職活動をし、就職したら多少のことは我慢するというのがよくある日本の若年層の姿です。
それに加えて、就職する時点では労働法の基本的なことが知られていません。三六協定は知っている人の方が珍しいし、「うちの会社には有給制度ありません」などと言ってしまう経営者もアレですが、そんなものかと思ってしまう人がそこそこいたりするのはみなさんもご存知でしょう。
ブラック企業は、このような買い手市場の中で、大量に採ってふるい落とすのを特徴としています。バブル経済の終わり頃、1990年に流行した用語「社畜」にはまだ飼い太らせるという意味がありましたが、現在のブラック企業に使い捨てにされる様は、「燃料」とか「乾電池」と言われるそうです。
IT産業の改善の道筋
IT産業の特徴である、いろいろ変な契約形態のことはみなさんよくご存知なので省略します。
まず、法律や制度の基本的なことを知ること、知らせることが大前提です。しかし、それが理解できても一人で解決するのは難しいです。失業しなければ平日は仕事で忙しいですし。そもそも、労使契約の関係が対等なわけがないから、商法とは違う考え方に基づく労働法があるわけです。そこを突破する力として、労働組合があります。
■ コンピュータ・ユニオン ソフトウェアセクション機関紙 ACCSESS 2017年12月 No.362 より