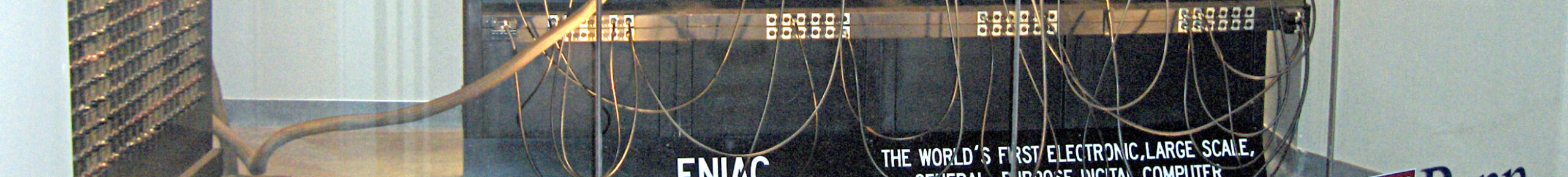カテゴリー: ブログ
-
生成 AI でプログラミング支援
組織部の作業で役に立っている生成AI ツールの Copilot がプログラミングの手伝いもやってくれるというこ…
-
3大映画配信サービス ザックリ比較
映画配信サービスは、いつでもどこでも観たい映画コンテンツが観られることで、映画コンテンツの史上最高の視聴数を記…
-
東京近辺で食べた世界の中華料理
Panda Expressチャオメン、オレンジチキン、モンゴリアンポーク 米国では有名なチェーンで、Googl…
-
ブラインドタッチについて
組合活動とは関係ない、「ブラインドタッチ」についての話題です。 先日、供給先の配属課の課内教育に「ブラインドタ…
-
原発は日本列島に向かない
関西電力高浜原発の3号機と4号機の稼働が20年延長され、60年の稼働が認可される記事が、5月29日に配信された…
-
情報処理試験会場でのリーフレット配布
4月21日に情報処理技術者試験が行われました。それに合わせてリーフレットの配布を行いました。 今回は拓殖大学の…
-
文化部だより
コロナの影響でしばらくの間、実際に対面であって行うリアルイベントは中止していた文化部ですが、昨年の大会後交流会…
-
どしゃ降りメーデー&交流会
2024年5月1日、第95回中央メーデーが代々木公園にて開催されました。平日で雨の予報が出ていたこともあり、電…
-
何の役にも立たないがクセになる YouTube チャンネル5選
皆様、YouTubeをどのくらい視聴されてますか。日本のユーザー数は、2025年には9,762万人に達すると言…
-
支部委員だより~親切~
人間、長く生きていると多くの難問に直面します。病気やケガ、仕事、保険、年金はどこにどう聞いたらよいかわからない…